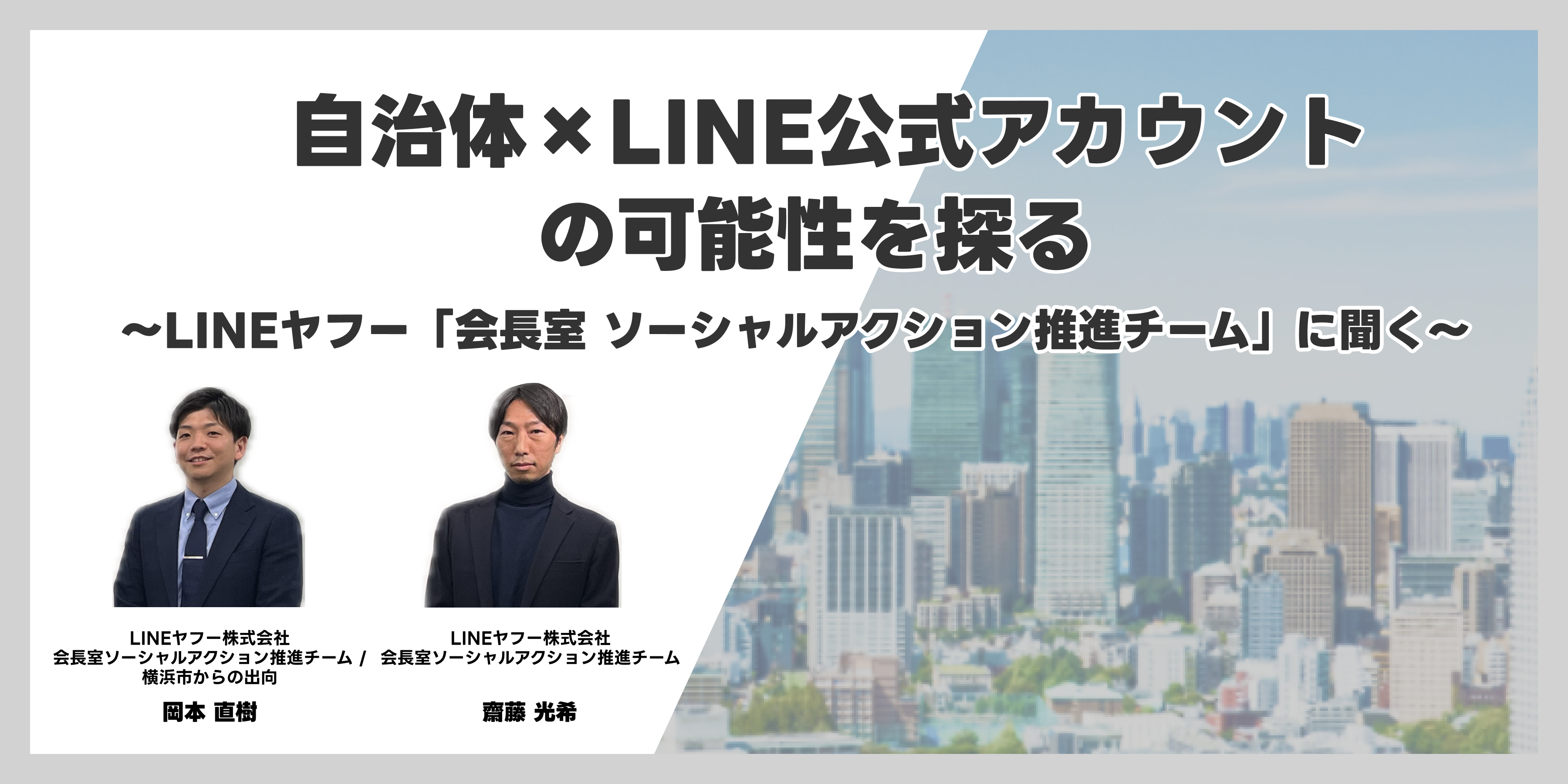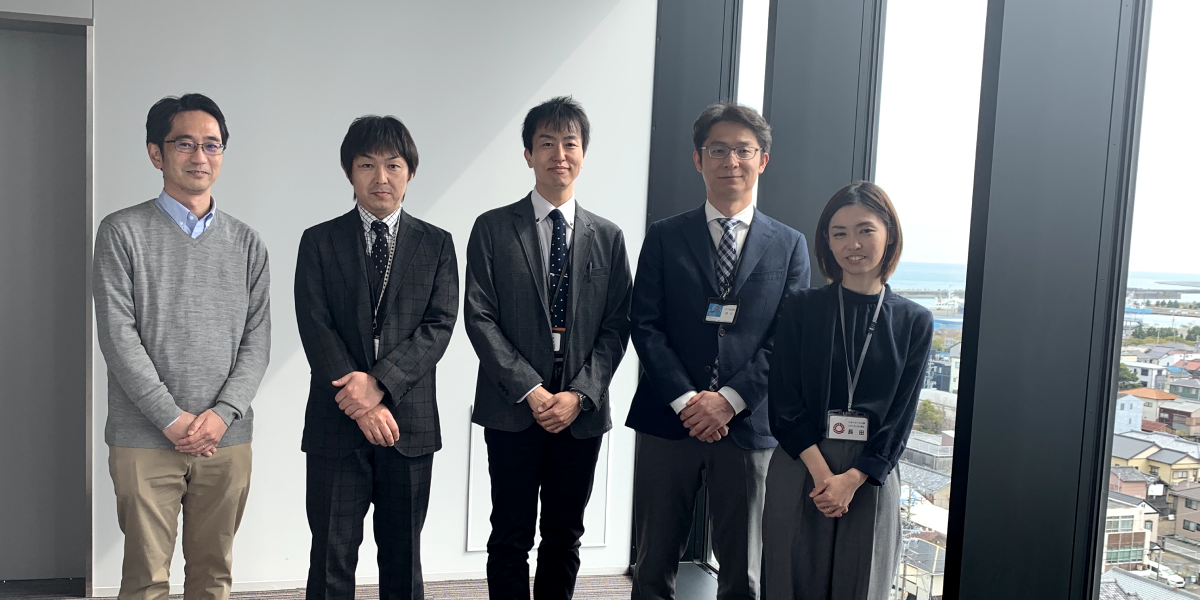災害対策にLINEを活用―神戸市の試み
大場 神戸市がLINE公式アカウント「神戸市災害掲示板」を導入することになった背景についてお聞かせいただけますか? これまで神戸市さんで取り組まれてきた防災対策や情報発信の課題などを踏まえ、どうしてLINEという手段に行き着いたのでしょうか。
近藤 神戸市では以前から、テレビ・スマートフォン、あるいは防災行政無線など、さまざまなチャネルを使って災害情報を市民の皆様にお伝えしていました。昨年からは、市のホームページ上に「リアルタイム防災情報※」という仕組みを整え、避難所情報や気象警報などを一元的に見られるようにもしています。
しかし、そうした取り組みはあくまでも「行政から市民へ」一方通行の情報発信にとどまっていました。災害規模が大きくなればなるほど、行政が全域の被害状況をリアルタイムで正確に把握するのは難しいんです。消防や救急に寄せられる119番通報も重要な情報源ですが、それだけでは把握しきれない被害が多々あると想定しています。
一方で、X(旧Twitter)やFacebookなどには市民が独自に被害状況を投稿しており、市としても情報収集の手段の一つとして活用をしていますが、投稿された情報の場所や真偽といった点を正しく評価するのが難しかったんですね。そうしたなか、より多くの方が日常的に使っていて、一定の個人責任をもって投稿しているツールであれば、災害時にも有効活用できるのではないかそう考えて、LINE公式アカウントに注目した次第です。
※ リアルタイム防災情報 :https://city-kobe.my.salesforce-sites.com/
大場 なるほど。SNSを活用して災害時の情報を相互共有するというアイデアは、昨今多くの自治体で注目されていますね。その中でもLINEを選んだ理由はなんだったのでしょうか?
近藤 はい。LINEは国内の幅広い世代で利用されています。神戸市でも多くの市民が日常的にLINEを使っていると想定できますし、何より使い慣れたツールなら、災害時でも迅速な投稿が期待できるというのが一番の決め手です。
また、「普段は使わないアプリをダウンロードしてもらうより、既に使い慣れているもののほうがハードルが低い」と考えたことも大きいですね。いわゆる“フェイズフリー“という概念(平常時・非常時を問わず利用できる)を重視すると、やはりLINEのような普及度の高いツールが適していると思いました。
防災情報の“双方向化“を目指した実証実験
大場 実際、神戸市では2019年(令和元年)から「SIP-KOBE実証訓練」という名前でLINE公式アカウントを運用し、災害時の情報共有を試みてきたと伺いました。この実証実験はいつ頃から、どのような形で行われていたのでしょうか?
近藤 令和元年から継続的に行い、最終的に2024年12月で「実証実験」という扱いは終了しています。SIP-KOBE実証訓練のLINE公式アカウントを通じて、台風や大雨警報、あるいは大雪警戒などの気象警報・注意報等が発令されたタイミングで、「皆さんの周りの状況を教えてください」と市民の皆さんに呼びかけ、被災状況や危険だと感じる状況を文字や写真で投稿していただきました。
実験期間中の登録者は最大でおよそ1万5,000人(※実際にはもう少し幅があります)に達し、台風・気象警報発令時などの投稿数は合計で1,000件を超える投稿が寄せられました。LINE公式アカウントを通じて寄せられた投稿は、投稿文からシステムがカテゴリ分けをし、地図上に可視化する仕組みになっていました。
大場 そのシステムは、神戸市だけで独自開発されたものなのでしょうか? また、投稿内容のチェックや管理はどうされていたのでしょうか?
近藤 システム部分はウェザーニューズ様に提供いただいたもので、AIが投稿内容のキーワードを判定し、「雨」「道の冠水」などカテゴリに応じて区分します。明らかに誤情報や不適切な投稿があった場合、管理者の判断で削除できる機能もありますが、実験期間中は偽情報らしきものが確認されることはほぼありませんでした。これも、LINEユーザーがある程度個人として登録・利用していることと関係があるのかもしれません。
大場 なるほど。SNS上での災害情報はどうしても「真偽が判別しにくい」という課題が挙がりがちですが、LINEの場合は比較的トラブルが起きにくかったということですね。では、実際に市民が投稿した情報は市民同士でも閲覧できる仕組みでしょうか? また、それを神戸市としてどのように活用してきたのか気になります。
近藤 はい。市民同士でも投稿内容を共有できる仕組みになっていまして、「自分の住む地域の被害状況がどうなっているか」等を確認し合えるようにしております。投稿内容からご自身の安全確保のために避難行動をとる判断材料にしていただきたいです。行政側としては、災害状況を把握するための手段のひとつとして活用しています。もちろん、あくまで119番通報が優先されるべき緊急事案もあるので、「何か危険を感じたら必ず119へ」というメッセージを送るなど、運用には注意を払っています。

実証実験で見えた効果・課題
大場 そのような形で実証実験を進めてきた中で、「思わぬメリット」や「想定外の課題」などはあったのでしょうか?
近藤 メリットとしては、「被害が大きい場所だけでなく、予想より被害が少ない場所の情報もわかる」ことが挙げられます。大雨警報が出ていても「この地域は案外ひどくない」という投稿があると、市全体の被災マップを俯瞰するうえでも非常に有益です。従来の一方通行型の情報発信だと把握できないリアルな状況が集まります。
一方で、課題はやはり「災害が起きないと情報が集まりづらい」ことですね。通常時にはあまり使われないアカウントですので、「そもそも登録してもらう」「いざという時に思い出して使ってもらう」ための啓発が必要だと痛感しました。普段からの周知が欠かせません。
大場 確かに、災害が発生しないとシステムを試す機会も少なく、利便性を実感しにくい部分はありますよね。登録者数を増やす取り組みとしては、具体的にどのようなことを考えていらっしゃいますか?
近藤 神戸市全体で運用している別のLINE公式アカウントとも連携し、「神戸市災害掲示板」の存在を周知する取り組みを進める予定です。また、地域の防災訓練のタイミングや梅雨・台風等のシーズン到来前に「投稿練習」を呼びかけるなど、市民の皆さんに操作体験してもらう機会を増やせればと考えています。今後はチラシや広報紙などを使った案内も強化していきたいですね。
大場 実証実験は2024年12月で終了し、それ以降は「神戸市災害掲示板」として本格運用されるとのこと。具体的には、どのようなアップデートや新機能を想定されているのでしょう?
近藤 現在の仕組みでは、市民同士の災害情報共有や、行政側による初動把握が中心ですが、今後は「利用者アンケート」を行い、「こんな機能があると助かる」「こういう情報を見たい」といった要望を収集しながらアップデートを検討したいと考えています。
これまでとったアンケートから、たとえば大雨による土砂災害など、災害危険度の高まりが登録された位置情報と合致すれば、避難するようプッシュ通知する機能については、実装されたら便利であるとアンケート結果が出ていますので実装を検討しています。
阪神・淡路大震災から30年となる2025年に向け、神戸市としても改めて防災を見直す機運が高まっています。市民同士が支え合い、行政のリソースも最大限に活かせるような仕組みづくりを今後も追求していきたいです。
大場 他の自治体や企業でも参考になるお話だと思います。もし、「今後LINEなどを使った防災システムを検討しよう」という自治体や企業にアドバイスがあれば教えてください。
近藤 一方通行の情報発信に限界を感じている自治体は多いと思いますが、いざ双方向化を図ると「投稿数が多すぎて対応できないのでは?」という声が上がりがちです。確かに、大規模災害が起こると投稿が膨大になる可能性はありますが、市民側で互いの投稿を閲覧して「ここは安全そうだ」「避難しやすそうだ」と自己判断につなげるだけでも、防災全体の底上げになり、自助・共助を促す仕組みの一つとして活用できると考えております。
そして、普段から誰もが使っているプラットフォームを採用することで、登録のハードルを下げるのが大切です。防災アプリをゼロから作るとなると、市民にダウンロードを促すだけで相当なコストと手間がかかりますし、使い方も覚えてもらわないといけない。そう考えると、「すでに多くの方がインストールしているLINEを使う」という選択肢は非常に合理的だと思います。
大場 本日は貴重なお話をありがとうございました。阪神・淡路大震災から30年を迎える節目に、神戸市のLINE活用がますます注目されそうですね。
近藤 こちらこそありがとうございます。災害対策は日頃の備えや意識づくりが何より大切です。LINEを活用した仕組みはまだまだ発展途上ではありますが、より多くの市民に活用していただけるよう、これからも改善を重ねていきたいと思います。
(取材日: 2025年3月18日: 取材/大場 沙里奈)